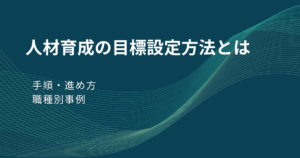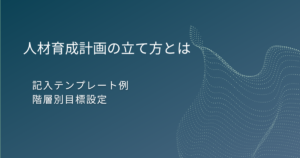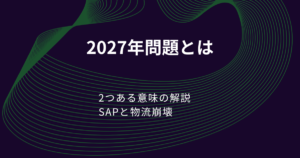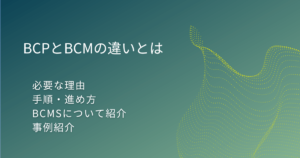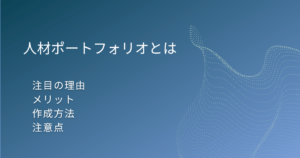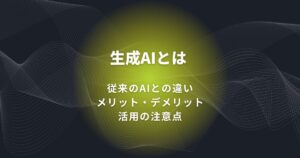Go To Market(GTM)とは
Go To Market(GTM)戦略は、新製品や新サービスを市場に導入する際、またスタートアップなどの新しいビジネスを開始する際に策定する新市場開発戦略のことである。3つの観点で解説する。
GTM戦略とマーケティング戦略の違い
GTM戦略は、新製品、新サービス、スタートアップ等の新しいビジネスを市場導入する時に、誰に、何を、どのように価値を届けるかを設計した戦略である。したがって、新しい製品・サービスに絞った1回限りの戦略になる。
一方、マーケティング戦略は、新製品や新サービスだけでなく、全製品とサービスを対象とした顧客価値創造戦略になる。マーケティング戦略は1度限り策定すればよいわけではなく、持続的に見直しし、顧客との関係構築を行うことで需要創造を図る。
GTM戦略とマーケティング戦略の共通点
両方の戦略にはいくつかの共通点がある。両戦略ともに、ターゲット市場と顧客の理解は必須である。そのために市場分析を行い、狙うべき顧客ニーズや未充足ニーズを明らかにすることが必要になる。
また、提供価値を定義することも類似点である。製品やサービスの提供価値と他社との違いを明確にすることで、差別化を図ることも共通点である。製品やサービスの単純な性能向上や価格の変更など、小手先の取組みでは顧客が選択してくれない市場環境となっている。
Go To Market(GTM)の重要性
既存製品やサービス、更には既存事業だけでは持続的な成長が難しくなっている産業が多くなる中、新製品や
新サービスの市場導入や、新規事業のローンチの戦略設計を目的とするGTMの重要性は年々増加していると言える。
4つの観点からその重要性を整理する。
市場との整合性
GTM戦略は、新しい製品やサービスが市場・顧客の要求と整合していることを確認することで、ターゲット市場・顧客に受け入れられる可能性を高めることができる。その結果、新製品の市場導入や新規事業のローンチをする際に関連するビジネスリスクを軽減することに役立つ。
リソースの最適化
日本企業のマーケティング計画においては、リソースプランが不明確なことが多い。予算配分だけでなく、必要人材や流通チャネルを含めた明確なリソース計画を描くことで、効果的な役割分担と経営資源の割り当てができる。
営業・販売部門に明確な計画と効果的に製品を販売するための考え方を提供するとともに、統合したキャンペーンを立案し実行することに役立つ。
焦点を絞ったメッセージング
市場での新しい製品やサービスの差別化に重要な価値提案について、一貫した説得力のあるメッセージを作ることが可能になる。提供価値の定義を行うだけでなく、どのように届けるかを設計するため、顧客接点において統合的なメッセージングが実現する。
その結果、より良い顧客体験を提供することができ、新しい製品やサービスに対す顧客ロイヤルティ獲得とブランド確立を促進することが可能となる。
戦略的な学びとフィードバック
新しい製品やサービスの市場導入や新規事業のローンチの戦略設計図に基づく取組みによって、市場の反応、競合他社の動向、顧客の潜在ニーズや未充足ニーズに対する洞察が深まる。その結果、新しいビジネスにおける意思決定の精度を高めることができる。
また、得られた学びをマーケティング戦略に統合することで、継続的な改善や顧客との関係性構築に役立てることができる。そのためにも、KPIを設定し、GTM戦略の施策をモニタリングする仕組みを構築しておくことが非常に重要となる。
Go To Market(GTM)戦略の策定の手順
GTM戦略の策定は、6つのステップで行うことができる。
ステップ1:解決すべき顧客課題の特定
新しい製品やサービスが成功する最も重要な要件は、解決すべき顧客課題が明確であることである。顧客の抱えている悩みや課題に応えて、顧客が望む価値を提供することが重要である。また、提供するタイミングも熟慮することが必要となる。
新製品・サービス開発の方法論としてプロダクトマーケットフィット(PMF)が挙げられるが、上市製品と市場ニーズがフィットした状態にどのように到達するかを考えることがGTMにおいても重要となる。そのためにも、PMFの状態を正確に理解することが必須となる。
ステップ2:ターゲット顧客の定義
解決すべき顧客課題とともに、ターゲットとする顧客を明確に定義することが重要である。重点顧客をより立体的に整理するためにペルソナを作成することをお勧めする。ペルソナを作成する時に必要な典型的な項目は以下の通りである。
ペルソナ作成に必要な項目例
- 基本情報(年齢/性別/居住地/家族構成)
- 職業
- 収入(年収/世帯年収/貯蓄額)
- ライフスタタイル(働き方軸、暮らし軸、消費・支出軸、趣味軸、時間配分軸など)
- 性格(行動特性/価値観/トレンドに対する感度)
- 興味関心ごと(趣味など)
- 対象製品・サービスに関連する現状課題・ニーズ(悩み/要望/不満など)
- 情報収集方法・メディア接触状況(各メディア/SNS /YouTube等)
- インターネット/スマホ利用状況・利用時間
重点顧客をより具体的にイメージすることは非常に重要であり、ペルソナと顧客プロファイリングを組み合わせることで、顧客分析を進めると良い。顧客プロファイリングとは、典型的な顧客像をデータ活用して描くことであり、ペルソナと両手法を活用することで定性的かつ定量的に顧客をイメージできるようになる。
ステップ3:競合調査と評価
顧客分析だけでなく、新しい製品やサービスを市場導入する際の競合他社の分析も行う必要がある。マーケティングにおいても競合他社との違いを明確にし、ポジショニングを設計するが、GTMにおいても必要な取組みとなる。
競合調査と評価の目的は、差別化されたメッセージ開発に向けた取り組みであり、顧客接点横断で統一的に展開すべきメッセージ要件を抽出する。その際、自社製品と競合他社との違い及び類似点、顧客の評価、満たされていないニーズ、顧客接点とメッセージを具体的に洗い出してみることをお勧めする。
ステップ4:キーメッセージ開発
次に、ターゲット顧客へ伝えたいキーメッセージを開発する。事前に開発したペルソナ(想定顧客像)に対応したキーメッセージ開発が必要であり、注意が必要である。
一律に顧客の未充足ニーズ解消だけを訴求することは安易であり、ペルソナ独自の価値観を踏まえた軸・切り口を考えることが重要となる。最終的には、キーメッセージは選択されたチャネルやコミュニケーション手法によって届けられるため、キーメッセージと合わせて、提供ストーリーを描くことも大切である。
ステップ5:顧客への届け方開発
GTM戦略を考える基本は、「誰に」「何を」「どのように届けるか」の3要素が必要となる。ステップ5は、まさに3つ目の要件であり、具体的な業務は新しい製品やサービスを届ける体制とチャネル設計になる。
体制とは、社内だけでなく販売店を含めたビジネスパートナーも対象となる考え方である。自社のリソースをどこに投入するか、外部パートナーの強みを最大限に生かしてどのように協働するかを明確にする。
また、チャネルは、販売チャネル、流通チャネル、コミュニケーションチャネルの3つの考え方を統合した概念である。営業、マーケティング、広報宣伝が連携し、最適な新製品・サービスの提供方法とメッセージの届け方を描く。
3つのチャネルの具体例
| チャネル | 具体例 |
| 販売 | 店舗、EC、直接販売、代理販売 |
| 流通 | 卸業者(一次、二次)、販売店、代理店、小売業者 |
| コミュニケーション | マスメディア(テレビ、ラジオ、雑誌など)、デジタルメディア(Web、SNSなど) |
ステップ6:販売計画の作成と実行
GTM戦略の狙いは、新製品や新サービスの販売であるため、ターゲット顧客に対してどのようにアプローチし、興味喚起を行い、いかにして潜在顧客を買い手である顧客へ変えるかが重要となる。その役割を担うのが、販売計画になる。
販売計画を具体化する際の4つの営業モデルを紹介する。各社の商品特性や事業モデルに合致するように、各営業モデルを組み合わせて展開することが必要となる。
4つの営業モデル
| 営業モデル | 具体的な取組み |
| セルフサービス | 顧客が自分の判断で、ECを通じて製品を購入する顧客はWeb、SNS、各種メディアを通じて希望の製品を探し、ECを通じて購入する流れが一般的な販売プロセスとなる営業チームは不要ではあるものの、ECへの流入を増やすためのマーケティングが必要となる |
| インサイドセールス | 非対面営業・内勤営業と呼ばれる取組みで、マーケティング活動で認識した見込顧客(リード)に対して電話やデジタルツールを活用してアプローチする顧客との関係づくりを行い、不満やニーズを把握した上で、興味喚起や製品購入の動機づけを行うインサイドセールスが販売する製品は、汎用製品や準汎用製品、モジュール製品などが対象となることが多い |
| フィールドセールス | 顧客へ自社の営業担当が販売する直販モデルである見込顧客の発掘から見積・提案を行い、最終的に受注・販売を行うモデルであり、営業活動への人件費・販売費投資が必要である一方、直接販売のため成功した場合の利益は大きくなり、顧客接点を直接持つことができるため、顧客データの蓄積と活用にも優れている |
| チャネルモデル | 自社製品を、ビジネスパートナーや商社が販売する代理店販売のモデルである自社で営業担当を配置する必要がないため手離れが良く、類似製品を販売している企業と提携することで、より効率的かつ効果的に販売することが可能となる代理店や商社との戦略一致を行い、販売活動のマネジメントや手数料設計が必要となる |
GTM 戦略の実行における留意点
まずは、関連部門とGTM戦略を共有し、協働することが重要である。そのためには、戦略の実行契約やプロジェクト計画を関係者が閲覧し、いつでも確認できる仕組みを構築することが重要である。
計画だけでなく、進捗状況もモニタリングし、現状実態を常に把握するとともに、課題解決に向けた素早いアクションを起こすことが肝要である。
次に、目標に対する達成状況を可視化し、ギャップ解消策を具体化することが重要である。そのためには、月次ではなく、週次でのマネジメントの仕組みづくりが肝になる。
GTM戦略のプログラムは、新製品や新サービスの上市から市場実感の把握と定着までの期間限定施策になる。そのため、目標達成に向けた進捗管理は重要な業務となる。
Go To Market(GTM)戦略のマネジメント
GTM戦略を成功させるためには、目標設定とKPIマネジメントが必要である。
最終目標と中間目標を設定するとともに、プロセス指標としてKPI(Key Performance Indicator)を定め、戦略施策の進捗状況と途中成果を確認し、課題認識を行い、解決施策を具体化することが重要となる。
目標が曖昧な場合は、戦略施策が有効かどうかが不明確になるため、改善活動がおろそかになる。目標設定をより有効に行うためのフレームワークを紹介する。
目標設定のフレームワーク:SMART
- Specific(具体的に):目標設定は、具体的に行うことが必要である
- Measurable(測定可能な):目標設定は、測定可能である必要がある
- Achievable(達成可能な):目標設定は、達成可能である必要がある
- Relevant(関連性のある):経営目標や経営戦略など組織の方向性との整合性が必要である
- Time-bound(時間制約のある):目標達成には期限があり、期限内の目標達成が必要である
プロセス指標として重要業績評価指標 (KPI)を設定し、ビジネスの成果目標の達成に向けた進捗を定量的に測定することが必要である。具体的には、成果創出に向けたプロセス指標を設定し、追跡することで課題を明確にし、改善策を立案し実行することで、最終的には目標達成に近づくことができる。
参考になるKPIを以下に具体例を挙げる。
- 年間経常収益ARR(Annual Recurring Revenue)、月次経常収益MRR(Monthly Recurring Revenue)
- 新製品・新サービスの売上高成長率(Growth rate)
- 新製品・新サービスの解約率(Churn rate)
- 売上高継続率NRR(Net Revenue Retention:売上継続率)
- 収益継続率GRR(Gross Revenue Retention:総収入維持率)
- CAC回収率(CAC payback period:顧客獲得コスト回収期間)
- 販売目標達成率
是非参考にして、GTM戦略の実行マネジメントを推進して欲しい。