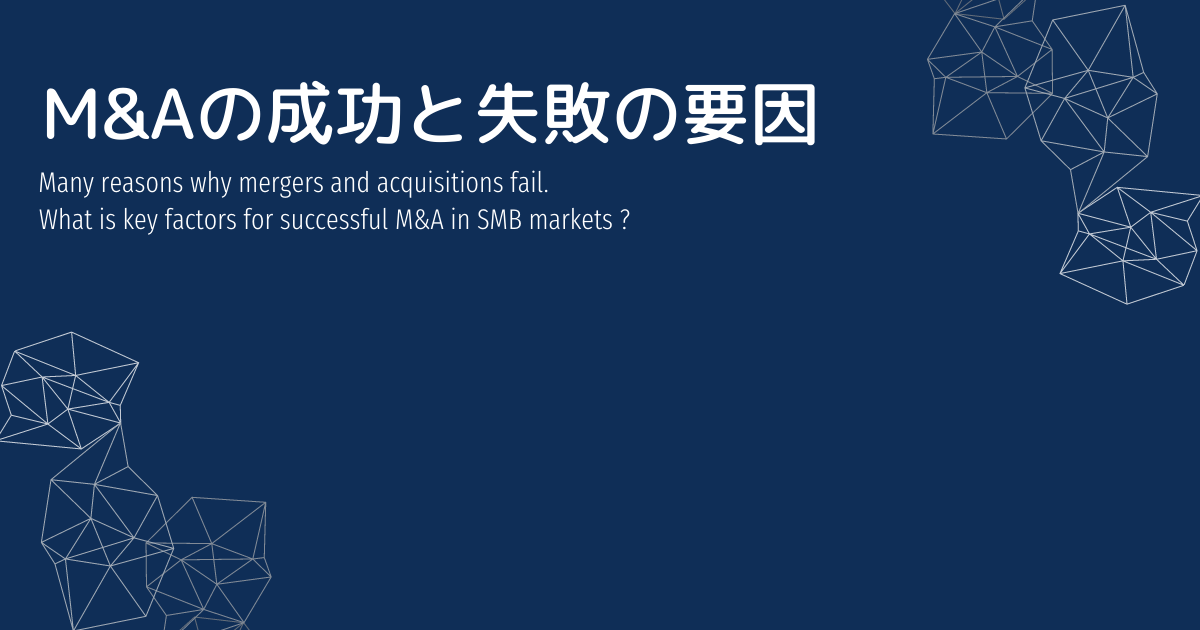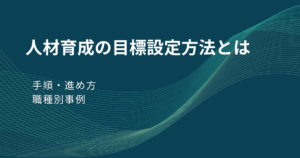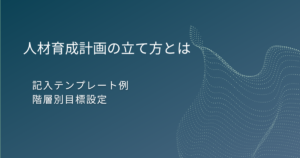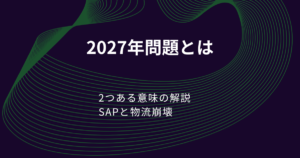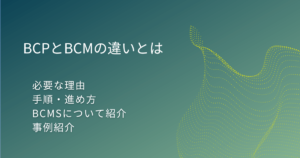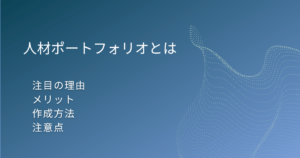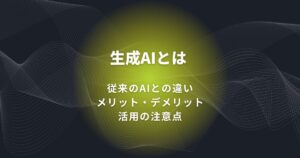国内のM&A最新動向
2019年末から始まった新型コロナウィルスの感染拡大。世界的なパンデミックを受け、2019年まで拡大基調だった日本国内のM&A件数は、2020年は一時的に減少した。しかし、2021年は増加に転じ、4,280件と過去最多を記録した。背景には、業績不振による企業及び事業の売却、不採算事業や非中核事業のカーブアウト、継続的な事業承継ニーズが存在する。2022年も同じ傾向が続き、前年と同水準の案件数となる見込みである。
中小企業のM&Aは既存事業とのシナジー効果を買い手側は重視
中小企業白書に興味深いデータがある。M&A実施意向を持つ企業に対して、希望する相手先企業の業種を調査したところ、買い手意向企業は、異業種で業種関連がない企業の買収意向は8.2%に対して、売り手意向企業は、異業種・業種関連がない企業への売却意向は30.7%と3倍以上の違いがある。買収側は、リスクの高い“飛び地”への進出はできる限り避けたい一方で、売却側は異業種への売却も検討する企業が多いと言える。こうした前提の違いが、相手先のデューデリジェンスや相乗効果の発現を難しくしていると言える。
M&Aマッチングビジネスの台頭について
M&Aの支援企業側へ目を移す。中小企業庁は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために、M&A支援機関登録制度を開始した。現在の登録機関数は法人ベースで2,072社となっている(FA業務のみ:236社、仲介業務のみ:88社、仲介・FA業務両方:1,748社の合計)。当事者にとって厄介なのは、仲介業務とFA業務の両方を生業としている業者が多いこと。売り手と買い手をマッチングさせる業務だけでなく、案件によっては当事者のファイナンシャルアドバイザーとしてM&Aの実行支援を行う企業が多い。したがって、中堅中小企業のM&A当事者は、買い手もしくは売り手の評価だけでなく、M&A専門業者の「目利き」も必要となる。
中小企業M&Aの目的について
難易度が高いM&Aだが、そもそもその目的は何か。実は、中小企業にとって、特にM&A経験が少ない企業において、M&Aの目的が不明確な場合が多い。昨今、M&Aに対するイメージは変化しており、買収・売却のいずれについても昔ほどマイナスイメージがない傾向がある(中小企業白書より)。結果、特に買い手企業においてM&A自体を目的化してしまう、一つのM&A案件への必要以上な過度な期待をかけるなどの課題が存在する。そこで、改めてM&Aの目的について、売り手と買い手の両方から整理する。
売り手企業の目的
売り手(売却企業)にとって、M&Aの目的は大きく3つに分類できる。1つ目は事業承継、2つ目は事業の選択と集中(経営資源の再配分)、3つ目が創業者利益の獲得である。
事業継承を目的としたM&A
事業承継は、後継者の不在(資質や能力不足を含む)を背景に、事業継続の危機からの脱却を意図することが多い。従業員の雇用を守りたいと考え悩んでいる経営者も多い。また親族内承継では、相続税・贈与税の問題や自社株式の分散などガバナンスの問題なども見受けられるため、第三者への売却を検討するケースも多く存在する。この場合、思いついてから短期間でM&Aを実行することは難しいため、最低3-5年間の計画に基づき事業承継プロセスを推進することが必要となる。
事業ポートフォリオ再構築を目的としたM&A
次に事業の選択と集中である。事業売却を検討する際、大きく2つのケースがある。1つは本業収益が悪化したため、不採算事業や非中核事業を売却し本業強化を進める目的である。もう一つは、事業ポートフォリオの再構築で、売却で得たキャッシュインフローを次世代事業への再投資に活用する目的である。この場合、前者においては強みの再認識・再定義が重要となり、後者においては次世代事業の見極めと成長戦略・ストーリーにおける位置づけを明確にすることが必要となる。
創業者利益の獲得を目的としたM&A
最後の創業者利益の獲得については、創業者オーナーの価値観や経営思想に依存することが大きいテーマである。また、創業者の持ち株比率により軋轢やトラブルが発生することもあり、注意が必要である。スタートアップやベンチャー企業の場合は、日本においてはM&AよりもIPOによるEXITが多い特徴があるが、今後はM&Aも増加すると思われる。この場合、創業時の創業者の企業価値への貢献は非常に高い一方で、事業拡大と成長に伴いEXITを検討する際は、キーとなる役員や従業員の貢献度合いが高くなることが多い。従って、こうした成長を支える従業員への還元やモチベーション向上の仕組みも検討することが重要となる。
買い手企業の目的
買い手(買収企業)にとって、M&Aの目的は売り手以上に多様であり、大きく5つ考えられる。1つ目は新たな収益源の獲得(多角化)、2つ目は市場シェア拡大(過当競争からの脱却)、3つ目は技術・ノウハウの獲得、4つ目は人材の獲得、5つ目は顧客基盤や販売網の獲得である。いずれも短期間で事業拡大と成長の実現を目標とした打ち手になる。昨今、事業会社がコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)を組成し、事業投資やVB投資により成長を実現しようとする動きが活発である。但し、企業買収は非常に難易度が高いため、各目的を達成するための留意点を整理しておく。
シナジー効果を見込んだM&Aについて
1つ目の新たな収益源の獲得であるが、飛び地になればなるほど目的達成ハードルは高くなる。周辺領域や自社と強みが被らない同業界でのM&Aが定石となる。但し、既存事業が衰退産業のため業態転換が必要な場合は、飛び地への進出も検討することがある。しかし、本業の行き詰まりを理由としたM&Aはうまくいかないケースも多く見受けられるため、今一度、自社の強みや収益改善余地の棚卸しを行うことを推奨する。
シェア拡大を見込んだ同業M&Aについて
2つ目の市場シェア拡大は、同業買収に近い取り組みである。分散型の市場特性である産業では有効で、過当競争を避けることができる。但し、これまで市場競争でしのぎを削ってきた相手と組むには相当な交渉と対話、株主価値向上策が必要となる。この場合、必要な着眼点は産業構造を変える、すなわち顧客への提供価値を変革する視点が重要となる。その際、市場シェアを構成する「その他」に目を向けてみることも重要である。分散型市場の場合、その他比率が高くなることが多いが、特徴ある企業や技術(もしくは新規参入者)が存在することもある。もう一つの着眼点は、市場自体を再定義すること。既存の市場定義ではなく、顧客視点に立って市場を再定義することで、新たな買収候補先が想定される可能性もある。いずれにせよ「顧客視点」が共通項となる。
人材・技術の獲得を見込んだM&Aについて
3つ目は技術・ノウハウの獲得、4つ目は人材の獲得であるが、両者は自社に不足しているリソースを獲得するという狙いで共通している。また、両者ともに「見えない資産」の代表格であり、M&A実務においても非常に評価が難しい。そのため、日常的に自社の技術・ノウハウ及び必要な人材要件を棚卸しし、見える化しておくことが重要となる。更に、市場感度の高いアンテナをはり、競争環境の動向を察知することが必要となる。いわゆる産業調査機能である。
顧客基盤拡大を見込んだM&Aについて
5つ目は顧客基盤や販売網の獲得であるが、分かりやすい反面、注意が必要である。本当に顧客基盤や販売網を買収によって獲得する意味・必要があるかどうか、熟慮する必要がある。また、BtoB事業とBtoC事業でもその意味合いは異なる。BtoBの場合はカニバリゼーションが起きたり、顧客から見た時に買収メリットが見えないこともあり得る。BtoCの場合は、ユーザーから見た既存ブランドの価値やイメージを棄損してしまうこともあり得る。市場シェア拡大と同様に、顧客視点で買収による相乗効果・メリットを明確にすることが重要となる。
中小企業M&Aを成功に導く進め方について
M&Aの意味合いは、上記で見てきた通り、売り手と買い手の双方にとって企業価値が向上することであり、M&A案件の実行中だけでなくM&Aの前後の活動が非常に大切である。また、成長戦略の一環としてM&Aを位置づけ、常に臨戦態勢を構築しておくこが重要と言える。
プレディール
- 成長戦略の一つの打ち手としてM&Aを検討し、M&A専門家や仲介会社、金融機関等からの最新の情報収集を行うとともに情報収集ルートを確立すること。
- 将来の市場環境や潮目を評価し、自社の強みの棚卸しとM&Aで獲得すべきリソースや組織能力を洗い出しておくこと。
- M&Aの専任担当(もしくは専任部署)を配置し、基礎知識や基礎能力を習得し、実践力を高めておくこと。また、外部専門家やM&Aアドバイザーを組織化しておくこと。
- M&A候補先をリスト化し、自社自らアプローチする先、仲介会社等からの提示企業など、優先順位付けを行うとともに、継続的な関係構築を図ること
ポストディール
- 統合準備室を組成し、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション:M&A後の統合プロセス)の実行計画を具体的に策定する。
- ①戦略の領域(市場/顧客戦略、事業/製品戦略)、②戦略実行基盤の領域(マネジメント、組織・人材、業務プロセス、情報システム)、③組織風土・コミュニケーションの3領域での統合計画と実行プランを具体化する。
- 重要度が高い施策を100日プラン(3か月)として整理、年間計画・2-3か年計画と時間をかけて行うべき施策を具体化する。
- 統合推進室が各領域の重点施策のモニタリングを行い、課題管理とPDCAの推進を行う。その際、両者協業体制を組み、組織風土の融合も行っていくことが重要。
M&Aは案件が起きたディール最中だけでなく、その前後の取り組みがその成否を分けると言っても過言ではない。M&Aプロセス全体でやるべき活動をイメージし、外部専門家の客観的なアドバイスや支援を得ながら、顧客価値を高め企業価値向上を実現できる組織能力を研鑽することが望まれる。